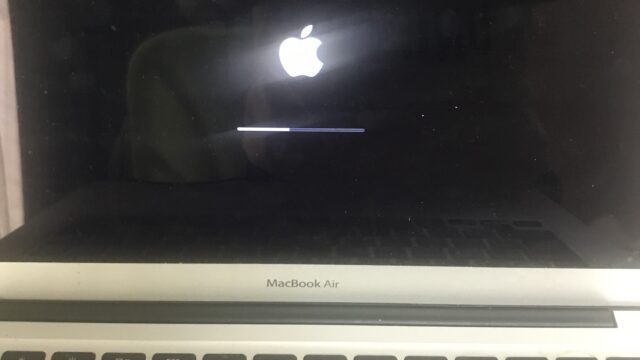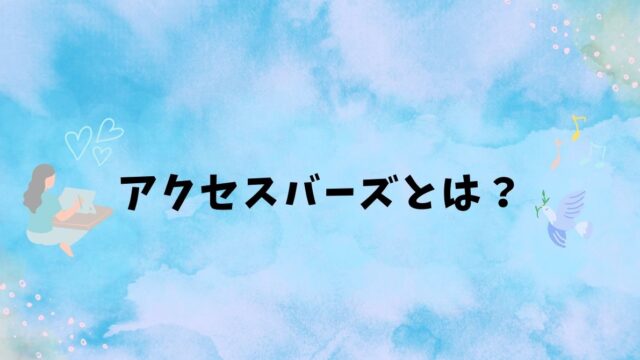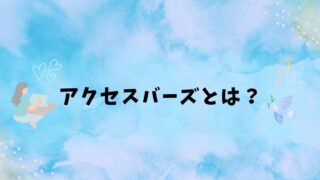「今年こそ新しい習慣を身につけよう!」と決意しても、三日坊主で終わってしまった経験はありませんか?
ダイエット、早起き、運動、勉強など、新しい習慣を定着させるのは簡単ではありません。
しかし、習慣化さえできれば、それは「努力」ではなく「当たり前」の行動になります。
では、習慣が身につくまでにどれくらいの期間が必要なのでしょうか?
よく「21日間続ければ習慣になる」と言われますが、実際には行動の種類によって異なります。
習慣化コンサルタント・古川武士さんの書籍によると、シンプルな行動習慣なら1ヶ月、身体習慣は3ヶ月、思考習慣は半年ほどかかると言われています。
本記事では、習慣化にかかる期間の目安を紹介しながら、無理なく続けるためのコツも解説します。習慣化に失敗しがちな方でも実践しやすい方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください!
習慣化にはどれくらいの期間がかかる?
「新しい習慣を身につけるには何日かかるのか?」が気になったことはありませんか?
意志力で毎日やるべきことをやろうとしても、ついサボってしまったり、やれなかったりします。
一方で習慣化していることであれば、毎日ほぼ必ずできてしまいます。歯磨きのように「やらないと気持ち悪い」と思えてしまうくらい自然に行動できるようになります。
一説によると「21日間続ければ習慣になる」と言われますが本当でしょうか?実際には習慣化の期間には個人差があり、行動の種類によっても異なります。ここでは、習慣化に関する代表的な説と、習慣の種類ごとに必要な期間を解説します。
① 21日間で習慣化できる?(マクスウェル・マルツ博士の説)
「習慣を作るには21日間が必要」と言われることがあります。
この説のもとになっているのは、形成外科医であるマクスウェル・マルツ博士の研究だと考えられます。
彼は、整形手術を受けた患者が新しい自分の顔になじむまでに約21日間かかることを観察し、この「21日間ルール」が広まりました。
しかし、これは行動習慣を形成する実験ではなく、実際の習慣形成には再現性が乏しいと考えられています。
ほかの研究では、習慣化には最低66日間が必要とされることが示されており、「21日で完全に定着する」というのは一般的には当てはまりません。
② 平均66日で習慣が定着する(ロンドン大学の研究)
習慣化に関する科学的な研究として有名なのが、ロンドン大学のフィリッパ・ラリー博士の研究です。
この研究では、被験者に新しい行動を毎日実践してもらい、どのくらいで「無意識にできる」レベルに達するかを調査しました。その結果、平均で66日間が必要であり、最短で18日、最長で254日かかったというデータが得られました。
この研究から、習慣化の期間には個人差があり、習慣の種類や環境によって大きく変わることが分かります。「何日で習慣が定着するか」に固執せず、最低2〜3ヶ月は継続する意識を持つことが重要です。
③ 習慣の種類による必要な期間の分類
習慣化コンサルタント・古川武士さんは、習慣を大きく3種類に分類し、それぞれに異なる習慣化の期間が必要であると述べています。
行動習慣の場合は1ヶ月
例:日記を書く、運動をする、毎日ストレッチをする
→ 比較的簡単に習慣化できるが、忙しくなると途切れやすい。
身体習慣の場合は3ヶ月
例:早起き、食生活の改善、姿勢を正す
→ 体のリズムや無意識の動作を変える必要があり、定着には時間がかかる。
思考習慣の場合は6ヶ月
例:ポジティブ思考、ネガティブな思考の排除、感謝の習慣
→ 考え方や価値観に関わるため、長期間意識し続ける必要がある。
習慣化の期間を理解し、焦らずに取り組むことが成功の鍵となります。
これらの分類は「習慣を作るには21日間が必要」という説とも、最短で18日、最長で254日という説とも矛盾しません。
習慣化のコツ
新しい習慣を身につけるには、単に続けるだけでは不十分です。我慢して無理に続けようとすると、途中で挫折してしまうことがよくあります。ここでは、習慣を無理なく定着させるためのコツを紹介します。
① 無理に頑張らない
習慣化において最も大きな落とし穴は、「意志の力」に頼ることです。
「毎日必ずやるぞ!」と意気込んでも、モチベーションは長続きしません。我慢して続けると、いずれ限界が来て「もう無理だ」と挫折してしまいます。
そのため、習慣化する際は「続けること」よりも「無理せず続けられる仕組みを作る」ことを意識しましょう。
例えば、運動を習慣にしたいなら「毎日30分走る」よりも「1日5分だけストレッチをする」といったように、最初は小さな行動から始めるのがポイントです。
② 毎日少しずつでも続ける(ゼロにしない)
習慣化の最も重要なルールは「ゼロにしない」ことです。例えば、「今日は忙しいからできない」と1日休んでしまうと、「昨日もできなかったし、まあいいか」とズルズルやめてしまうことがよくあります。
そのため、どんなに小さなことでも「少しだけやる」ことが大切です。
例えば、読書を習慣にしたいなら、時間がない日は「1ページだけ読む」。あるいはもっと負荷を軽くするなら、「本のページを開いて1行だけ読む」でもいいんです。それでもゼロにはなりません。
筋トレなら、やる気がない日は「腕立て伏せを1回だけする」といった具合です。
このように、少しでも行動することで「続ける」という流れを維持することができます。
ハードルを下げ、「もっとやりたい」と思える状態を作ることで、自然と習慣が続きます。
③ 休むのは1日まで
習慣を途切れさせる最大のリスクは、「2日連続で休むこと」です。
先述のロンドン大学のフィリッパ・ラリー博士の研究によると、1日休む程度なら習慣が崩れることはないのですが、2日連続で休んでしまうと「やらないこと」が新しい習慣になりやすいことがわかっています。
そのため、「どうしてもやる気が出ない」「忙しすぎる」というときでも、最低限の行動を続けることが大切です。例えば:
「運動できない日でもスクワットを1回だけやる」
「勉強できない日は単語を1つだけ覚える」
こうした小さな行動を続けることで、習慣を維持することができます。
④一度に習慣化するのは1つまで
「運動も読書も英語の勉強も全部習慣にしたい!」と考えるのは良いことですが、同時に複数の習慣を取り入れるのはNGです。
人間の意志の力には限りがあり、一度に多くの習慣を始めると負担が大きくなりすぎてしまいます。
ただし、例外的に「ルーティン化できる行動」であれば、一つのまとまりとして習慣にすることができます。
例えば:
「朝起きたら、散歩 → 読書 → 瞑想をする」
「寝る前にストレッチ → 日記を書く」
このように、関連する行動をセットにして習慣化することで、一つの流れとして無理なく続けられます。
⑤「Why(なぜやるのか)」を明確にする
習慣を続けるためには、「なぜそれをやるのか?」という目的(Why)が明確であることが重要です。
例えば、「カフェインをやめたい」と思っていても、「なんとなく健康に良さそうだから」ではモチベーションが続きません。しかし、「カフェインを断つことで睡眠の質が向上し、日中の集中力が上がる」と具体的なメリットを知ると、続ける意欲が高まります。
「その習慣を続けることでどんなメリットがあるのか?」**をしっかり理解し、意識することで、習慣化がスムーズに進みます。
習慣化に役立つアプリ/ツール
習慣化の成功には、「継続」と「可視化」が大きな鍵となります。
中でも、自分の行動を記録するタイプのアプリは、習慣を維持するモチベーションを高めてくれる強力なサポーターです。ここでは、私が実際に使ってみて効果を感じているアプリと、その他おすすめのツールを紹介します。
① 瞑想タイマー:誰でもできる瞑想・マインドフルネス

毎日瞑想をする人にとって便利なアプリ。タイマーを設定することで瞑想のスタート・終了を明確にできるだけでなく、「今日何分瞑想したか」が自動で記録されます。
数字として積み重ねが見えることで、「今日はやろう」という気持ちが生まれやすく、無理なく瞑想習慣が続きやすくなります。
毎回の瞑想後に「ひとことメモ」で感想を残すと、自己内省にもつながります。
無料でも、ほぼ問題なく必要な機能が使えます。使い終わったあとに広告が流れますが、見ないでそのままアプリを落としてしまえばそれで特に問題ありません。
②毎日まめ
「感謝日記」「今日のよかったこと」など、思考や気持ちを整える習慣にぴったりの記録アプリです。
シンプルで見やすいデザインなので、アプリが苦手な人でも使いやすく、1行日記や感情ログにも最適。思考の習慣化(ポジティブ思考など)を身につけたい方にとてもおすすめです。
夜寝る前に3分だけ使う「一日を振り返るタイム」を習慣にすると、安眠や心の安定にもつながります。
こういった毎日の記録の習慣化については下記の記事でも詳しくまとめました。
→ ジャーナリングの効果がない理由とは?メリット・デメリットと続けるコツ
③ 歩数計アプリMaipo
毎日の「歩く」を習慣化したい人には、スマホの歩数計アプリが非常に役立ちます。
スマホを持って歩くだけで自動的に歩数が記録されるため、何も意識せずに「記録」が残せるのが大きな利点。毎日の達成感が数字で見えるため、継続のモチベーションになります。
「昨日より100歩多く」を意識するなど、小さな目標を立てることで、ゲーム感覚で楽しく続けられます。
私が使っているのはMaipoというアプリです。無料で必要な機能はすべて使えます。
→Google play(Android)はこちらでダウンロード
④みんチャレ
匿名の5人1組でチームを作り、習慣化したい行動を「毎日報告し合う」アプリ。
社会的プレッシャー(=良い意味での監視)が働くことで、サボりにくくなり、継続力が格段に上がります。
似た目標を持つチームを選ぶと、モチベーションの共有ができて続けやすいです。
悪い習慣をもたらすアプリはアンインストール
逆に、アプリの中には悪い習慣をもたらすものもあります。
XやInstagram、YouTubeなどのSNS関連。
あるいはスマホゲームなどもハマると時間をとられがち。
スキマ時間にちょっとした時間つぶしや楽しみを提供してくれるものではありますが・・・
少しのつもりが、そこに多大な時間を費やすことになってしまうことも。
これもまた、習慣化の力が悪い方向に働いてしまいます。
こういった悪い習慣をもたらしていると感じたものは、アプリをアンインストールするのも手です。
また、楽しみでSNSやゲームをするのは構いませんが、取り組む時間は十分なコントロールが必要です。
まとめ
習慣化を成功させるためには、無理をしないこと、ゼロにしないこと、小さく始めることが大切です。また、「休むのは1日まで」「習慣は1つずつ」などのルールを守りながら、自分に合った形で続けることがポイントになります。
さらに、「Why(なぜやるのか)」を明確にすることで、モチベーションを維持しやすくなります。
アプリなどもうまく使うと効果的ですが、悪い習慣をもたらすアプリもあるので要注意です。
習慣化のコツを活かして、新しい行動を無理なく定着させましょう!